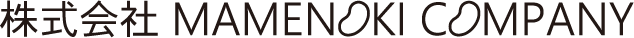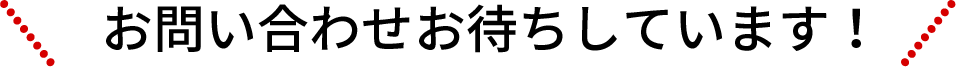2025年7月の記事一覧
チラシの印刷費用はいくら?相場価格とコストを抑えるポイント
WEB広告が主流な昨今ですが、チラシのような紙媒体の宣伝方法も多くの場面で活用されています。一方で紙媒体は、印刷費がどれくらいのかかるのかが気になるところ。チラシの印刷費用の相場はどれくらいなのか、コストを抑えるポイントなどをご紹介します。
チラシ印刷費用の相場はどれくらい?
チラシの印刷費用は、印刷する部数や仕様、印刷会社などによっても大きく異なります。たとえばA4サイズで片面カラーの印刷をする場合、以下のような価格帯が目安になります。
部数 印刷費用の目安
- 1,000枚 約6,000〜10,000円
- 5,000枚 約7,000〜20,000円
- 10,000枚 約25,000〜40,000円
ネット印刷ではより安く印刷できるので、200部で4,000〜6,000円というところもあります。しかしサイズや印刷枚数によっても料金は変わるので、必ず見積もりを取り確認しましょう。
印刷料金が変動する6つの要素
チラシ印刷の料金は、次の項目によっても大きく変動します。
(1)部数
印刷枚数が多くなるほど、1枚あたりの単価は下がります。
例えば、1,000枚印刷で1枚あたり10円でも、10,000枚印刷では1枚あたり3〜5円程度になることもあります。コストを抑えることを重視する場合は、まとめて印刷するのが基本です。
また印刷費用の中には、印刷作業にかかる基本料金が含まれています。この基本料金は、印刷枚数にかかわらず一定の金額がかかるので覚えておきましょう。
((2)用紙のサイズ
一般的にA4サイズが最も標準的で安価ですが、B4・A3など大判になればなるほど価格は上がります。逆にA5やB6といった小型サイズにすれば、コストを下げやすくなります。
((3)印刷面とカラー設定
チラシを両面印刷にするのか、片面印刷にするのか、またカラーにするのかモノクロにするのかによっても料金は変動します。両面印刷やカラー印刷は、インク量や工程が増えるためその分費用も上がります。
- ・片面モノクロ:最も安価
- ・片面カラー:標準的
- ・両面モノクロ/両面カラー:最も高価
(4)印刷加工の有無
印刷をする際、イメージに合わせてさまざまな加工ができます。しかし加工は追加料金となるので、その分費用は高くなります。具体的には、次のような種類があります。
- ・折り加工(二つ折り、三つ折りなど)
- ・ミシン目加工(クーポン切り取りなど)
- ・PP加工(ポリプロピレンフィルムを貼り付ける加工。ツヤ出しや耐久性UP)
- ・すじ入れ(厚い紙を折りやすくするために折り目を入れる加工)
- ・角丸(印刷物の角を丸くする加工)
- ・箔押し(箔を熱と版を使い、紙に圧着・転写させる加工)
- ・浮き出し(版の形に浮き出す加工)
(5)紙の材質
紙質によっても、価格が異なります。紙の材質には次のような種類があります。
- ・コート紙(表面がツルツルしていて、光沢のある用紙)
- ・マット紙(光沢がなく、つや消しコーティングが施された用紙)
- ・上質紙(表面に塗料が塗られていない、光沢やツヤの少ない用紙)
- ・ケント紙(表面がなめらかでやや硬め、白色度が高い用紙)
- ・マットポスト(マット紙のなかでも厚みがある用紙)
- ・アートポスト(表面に光沢があり厚手、カラー印刷が鮮やかな用紙)
(6)納期
「即日印刷」や「特急仕上げ」など、納期を早めに設定するスピード納品サービスを選ぶと、追加料金が発生するケースがあります。コストを抑えたい場合は、期日に余裕を持ち発注することで節約できます。
チラシ印刷費を抑えるポイント
コストを抑えながらチラシを制作したい場合、1枚1枚の印刷費を節約する必要があります。しかしチラシ自体のクオリティも落としたくないものですよね。どのようなことに気をつければ、チラシの印刷費を抑えることができるのでしょうか。
必要な部数を見極める(無駄な余剰在庫を作らない)
チラシが余ってしまうことが、最も費用が無駄になってしまいます。チラシを配るエリアの範囲はどれくらいが適当なのか、配布エリアの住民数はどれくらいなのか、ターゲットをしっかり絞っているのかなど、必要な印刷部数を見極めることが大切です。
用紙を小さいサイズに変更する(例:A4→A5)
紙のサイズを小さいものに変更すると、その分費用も安く抑えることができます。
紙が大きければその分載せられる情報も多く、文字も大きくできるので高齢の方も読みやすくなるでしょう。しかしサイズが小さいほうが手に取りやすい、持ち運びやすいというメリットもあります。チラシの内容やターゲット層を勘案し、サイズを小さくしてみることも検討しましょう。
モノクロや片面印刷を活用する
カラーではなくモノクロにする、両面ではなく片面印刷にするというやり方も、費用を安く抑えることに有効です。
モノクロでもデザインによっては、十分印象的なチラシに仕上げることができます。
加工を省略する(最低限でシンプルに)
チラシに加工がついているとオシャレになったり、インパクトが強くなったりなど、ワンランク上の印象に仕上がります。しかし情報を伝えることに、必ずしも加工は必要ではありません。加工をつけることよりも、チラシの内容がシンプルで読みやすいことのほうが重要です。そのため加工はつけないシンプルな仕上がりにすることで、コストを削減することができます。
「付け合わせ」で印刷する
「付け合わせ」とは、1枚の印刷用紙に複数の印刷物をまとめて配置して印刷する方法のことです。印刷した後に裁断(カット)し、それぞれのサイズに仕上げます。まとめて印刷できるので用紙代やインク代、印刷機の稼働コストが減り、印刷回数が減るので作業時間も短くなります。印刷業界でよく使われるテクニックで、コストを削減したり、効率化を図ったりすることができます。一方で色数や刷り色、紙の厚さや種類が異なるものは付け合わせできないので、注意が必要です。
複数の印刷会社で見積もりを比較する
印刷会社によっても、料金体系はそれぞれ異なります。まずは複数の印刷会社に見積もりをとり、比較検討してみましょう。印刷部数や条件によっては、必ずしもネット印刷のほうがお得とは限らないので注意しましょう。
印刷会社選びの着目ポイント
安さ重視で印刷会社を選んでしまうと、「イメージとは違った」などと思わぬ失敗をしてしまうこともあります。
料金以外にも、これまでの受注実績を確認しておくことは非常に重要です。実績数やこれまでに印刷してきたもの、実際の利用者からの口コミなども確認し、安心して依頼できる会社なのかチェックしておきましょう。とくに、こだわりのポスターやパンフレットなど特殊加工を施したいものなどは、過去に同様の加工を手掛けたことがあるか確認することをおすすめします。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「チラシの印刷費用を抑えたい」「コストを抑えながら反響を出したい」とお悩みの方は、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。 チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
梅雨時にポスティングはNG?効果的な雨対策と注意点
雨が降ると「チラシが濡れてしまうのではないか」「そもそもポスティングしないほうがよい?」と心配になるかもしれません。特に梅雨の時期のポスティングには、何に気を付ければよいのでしょうか。チラシを濡らさない雨対策や、配布時の注意点を解説します。
雨の日のポスティングは避けた方がよい?
雨の日のポスティングはチラシが濡れやすく、チラシがしわしわになってしまったり、破けやすくなってしまったりと、取り扱いに注意が必要です。濡れてしわしわになったチラシや文字がにじんでしまったチラシは読む気になれず、そのまま捨てられてしまう可能性が高まります。
さらにはチラシの投函時、雨の雫でポスト内やほかの郵便物も濡らしてしまうリスクも発生します。ポスト内が濡れてしまうと、クレームの原因になりかねません。
また雨の日は作業効率が落ちるなど、雨の日にポスティングをするのは原則避けた方がよいでしょう。
しかし梅雨のように長期にわたり雨が続く季節は、その間まったくポスティングしないわけにもいきません。雨の日でもポスティングを行う際は、チラシを濡らさない対策や工夫が必要となります。
チラシが濡れないための工夫【雨対策グッズ】
雨の日に最も注意すべきことは、雨でチラシを濡らさないようにすることです。雨天のポスティング時に活躍する、雨対策グッズをご紹介します。
ビニール、タオル
チラシを持ち運ぶときは、ビニール袋など濡れないものに入れましょう。さらに上からタオルで巻いておくと安心です。万が一かばん内に水が入ってしまっても、チラシが濡れるのを防ぐことができます。
・プラスチックファイルを活用する
クリアファイルなど、プラスチック素材のファイルにチラシを入れると、雨に濡れにくくおすすめです。特に蛇腹ファイルのように仕切りがあるファイルは、チラシの枚数を確認・整理しやすいでしょう。
・防水・撥水加工のかばん
雨天時のかばんは、防水・撥水加工のものがおすすめです。雨に濡れても中に浸水しにくく、チラシも濡れません。防水・撥水加工ではない場合でも、リュックカバーがあると安心でしょう。
配布スタッフが濡れない工夫
チラシを濡らさないだけでなく、配布スタッフ自身が快適に作業をできるような防水対策も行いましょう。
レインコート+防水シューズ
雨具は両手が空いたほうが作業効率がよいので、傘よりもレインコートを着用することをおすすめします。また上だけでなく、ズボン型のレインコートも着用すると濡れにくく動きやすいでしょう。
また雨の状況によっては、レインコートだけでは足らないこともあるかもしれません。その日の天気予報に合わせ、折り畳み傘や長傘も持参すると安心です。
また足元は防水シューズや長靴を着用しましょう。万が一シューズ内に浸水した場合に備え、替えの靴下を持っておくのもよいでしょう。
タオル
チラシを濡らさないためのタオルとは別に、配布スタッフが使用するタオルも用意しておきましょう。手が濡れてしまうとチラシも濡れてしまいます。手や体をすぐに拭けるよう、出しやすいところにタオルを準備しておきましょう。
雨の日の安全管理に注意
雨の日は見通しも悪くなるため、安全管理にも注意を払う必要があります。
滑りにくい靴
雨の日は滑りやすいので、靴は滑りにくいものを選びましょう。長靴やレインブーツ、トレッキングシューズなどがおすすめです。
衝突に注意
天候が悪い日は、車やバイクなどのドライバーは見通しが悪くなります。また配布スタッフや通行人も、傘など雨具を持っていると周囲への見通しが悪くなります。そのため思わぬ衝突などが起こる危険性も。交通量や通行人が多い道などは特に、周囲に十分注意をはらいましょう。
熱中症対策
梅雨の時期は気温が下がる傾向にありますが、湿度は高く、蒸し暑く感じる日もあります。特にレインコートを着ていると湿気がこもりやすく、より暑さを感じるでしょう。そのため梅雨の時期でも、熱中症対策は忘れずに行いましょう。定期的に水分を摂るなど、休憩することが大切です。
梅雨の時期に効果的なポスティング戦略
梅雨の時期は客足が遠のいてしまいがちです。しかし梅雨を逆手にとったポスティング戦略を行うこともできます。梅雨の時期におすすめなポスティング戦略をご紹介します。
ターゲット地域の選定
梅雨の時期は、ターゲット地域を見直すことも有効です。例えばできるだけ短時間に配布が終わるよう、住宅密集地を狙ってポスティングをする、屋根付きポストが多い地域を選定する、雨の影響を受けにくいマンションを中心にポスティングする、といった具合です。
配布時間帯の工夫
梅雨だからといって、毎日雨が降るとは限りません。事前に天気予報を確認し、降水量の少ない時間帯を狙いポスティングしましょう。曇り~小雨の時間帯に配布することで、チラシが濡れるリスクを避けることができます。
在宅率の高い層を狙う
雨の日は外出を控える人が多く、在宅率が高まります。主婦や高齢者、テレワーク層が多く住むエリアなど、在宅する人が多い層を狙って配布するのも有効です。
チラシを防水加工する
水に濡れることが大敵なチラシですが、ラミネート加工をしたり、防水紙を使用したりするなど、チラシ自体に防水対策をするのもおすすめです。多少雨で濡れてもしわしわになる心配がないので、クレームの予防や作業効率アップを図れます。
梅雨に合わせたキャンペーンチラシで反響UP
雨の日はマイナスなことばかりではありません。雨の日であることを逆手にとったキャンペーンを実施することで、集客アップすることもできます。
「雨の日限定クーポン」をチラシに付ける、タイムセールを実施する、「雨の日にチラシを持参すると〇〇をプレゼント!」など、雨の季節だからこその特別感を付けてみるのもおすすめです。
状況によっては中止する判断も必要
あまりにも雨がひどいときなどは、思い切って中止する判断も必要です。どの程度の雨であれば中断するのか、別の日に変更できるかなど、事前に依頼主と確認しておきましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは、クレームにつながりやすい雨天時のポスティングは行わず、納期に間に合うよう配布スタッフの管理を行っています。
また、教育がゆき届いた経験豊かな専属の配布スタッフを配備することで、クレームにつながらないよう注意しながら、細部にまで気を配ったポスティングを実施しています。
クレームを避けたい方、雨の日のポスティングに不安がある方は、ぜひ一度日本ポスティングセンターへご相談ください。
また日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、ポスティングの投函方法をはじめ、チラシのキャッチコピーやデザインなど、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
この記事を読んで日本ポスティングセンターのポスティングに興味を持たれたなら、下記までお気軽にお問い合わせください。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206