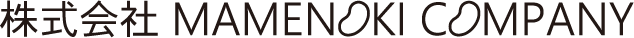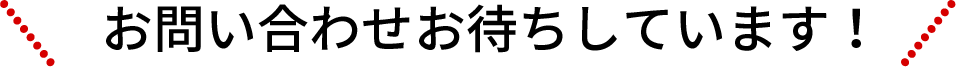2025年記事一覧
【年末のご挨拶と定休日について】
激動の一年、
新たな年が、皆様にとってより一層の躍進の年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
-----年末年始定休日のご案内-----
誠に恐れ入りますが下記の期間は年末年始休暇を頂戴します。
2025年12月27日(土)-2026年1月4日(日)
2026年1月5日(月)より通常営業とさせていただきます。
期間中に頂きましたお問い合わせは1月5日以降に順次対応させていただきます。
年末年始期間に配布をご依頼頂いておりますお客様
期間中、クレーム等のご入電がございましたら
メールもしくは担当者へお電話下さいませ。
ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
「ポスティング×QRコード」で反響アップ!あえて紙が効く理由
NS広告や動画広告など、私たちの周りには常に広告があふれています。しかし多すぎる広告に消費者は疲れ、心が動かなくなっている現実も。そこで近年、紙媒体が見直されています。ポスティングとQRコードを掛け合わせた、効果的な販促方法を解説します。
「記憶に残る」のは、画面ではなく“紙の質感”
スマートフォンの画面上で見る広告とポストに届いたチラシ、どちらが印象に残るでしょうか。この問いの答えとして、多くの調査で「紙の方が記憶に残る」という結果が出ています。
その理由のひとつが、「五感で触れられる」という点です。紙には質感、重さ、手触り、インクのにおいなど、スマートフォンの画面にはない「情報の厚み」があります。人は目だけでなく、手で触れた情報をより強く記憶する傾向があるため、紙のチラシは心理的にも印象に残りやすいのです。
また紙の広告は、「受け取りを拒否されにくい」ことも大きな特徴です。スマートフォンの広告はワンタップで閉じられますが、ポスティングチラシは自宅のポストに直接投函するため、一度は必ず手に取ってもらえます。そしてその一瞬の接触で、写真やキャッチコピーのインパクトから印象に残る可能性が高まります。
さらに紙は「保存性」も高いメディアです。チラシは捨てない限り手元に残るため、何度も見返してもらえるチャンスがあります。チラシに関心がある人であれば机の上に置いておいたり、冷蔵庫にマグネットで貼っておいたりするでしょう。
このように「あとで見返せる」という特性はデジタル広告になく、紙媒体ならではの強みとなります。
特に飲食店や美容室、塾やクリーニング店などの地域密着のビジネスにとっては、こうした生活導線の中での再接触が成約に直結します。 そのため近年「紙媒体の広告」、つまりポスティングが見直されているのです。
中小企業こそ、紙で「地域との距離」を縮めよう
全国展開する大手企業とは違い、中小企業にとって最も重要なのは「地域との信頼関係」です。そのためには地域の住民に自社のサービスを知ってもらい、親近感を持ってもらうことが欠かせません。ポスティングチラシは、まさにその信頼づくりの第一歩となります。
例えば地域の飲食店であれば「地元の食材を使った新メニューのお知らせ」、リフォーム業者であれば「近隣の施工事例紹介」など、身近な話題を発信できます。地元の人に「この会社、うちの近くにもあるのだ」と親近感を持ってもらうことが、来店や問い合わせにつながります。
さらに、紙のチラシは「誠実さ」や「安心感」を伝えることにも効果を発揮します。インターネット上の情報は匿名性が高く、「本当に信頼できるのか分からない」「いざというときに対応してもらえるかわからない」という不安を持たれがちです。
一方で住所・電話番号・顔写真入りの紙のチラシには、実在する会社であり、なおかつ場所が分かるという安心感が伝わります。「所在地が近所だからこそ、なにかあったときでもすぐ対応してもらえるだろう」「この人たちにお願いしてみよう」と思ってもらえる温度感は、デジタル広告では再現できません。
「紙×QRコード」で反響率をさらに高める
とはいえ、紙だけで完結する時代でもありません。
現代の消費者は、チラシを見たあとにスマートフォンで検索して詳細を確認するのが当たり前となっています。つまり「紙」と「デジタル」の橋渡しができる設計こそが、これからのポスティング成功のカギになります。そしてその中心となるのが「QRコード」です。
QRコードをチラシに掲載することで、ユーザーはワンタップでオンラインへアクセスできます。
問い合わせフォームや公式LINE、予約ページやGoogleマップなど、目的に合わせて誘導先を工夫すれば、反響率を大きく高めることができます。また逆に、SNS広告を見た人にエリアを絞って再度チラシ配布するのも効果的でしょう。
【QRコード活用の具体例】
飲食店:QRコードからメニュー表・ネット予約ページへ誘導
不動産会社:物件一覧ページや動画内見へリンク
美容室・エステ:初回限定クーポンをLINE登録特典として配信
学習塾・スクール:体験申込フォームへ直結
「紙を見て、スマートフォンで調べてから行動する」という流れは、現代人の行動習慣のスタンダードになっています。しかし自分で検索するには手間と時間がかかるため、「気になるけど、あとで検索しよう」と忘れられてしまうかもしれません。
QRコードを活用すれば、チラシを見たその瞬間にアクションを促すことができます。ワンタップで完結できる導線があるだけで、反響率は格段にアップするでしょう。
効果を高める「配置」と「見せ方」
効果を高めるには、ただQRコードを載せればよいというわけではありません。消費者の行動を促す言葉を添えましょう。
「今すぐアクセス」、「限定クーポンはこちら!」などの一言を添えることで、QRコード読み取り率が大きく変わります。またチラシの背景とQRコードのコントラストを明確にする、周囲に余白を確保するなど、QRコード自体を見やすくすることで読み取り精度も向上します。
さらに、QRコードのリンク先体験も大切です。スマートフォンで開いた瞬間に特典や申し込みボタンが見える構成にすることで、離脱を防ぎ、反響率を高められます。実際に飲食店のチラシで、「QRコードから予約でドリンク1杯無料」と掲載したところ、アクセス数が従来の3倍に増えたという事例もあります。
「紙」と「デジタル」のいいとこどりが販促の新定番に
ポスティングチラシはただ情報を伝えるだけでなく、「手に取ってもらう」「印象に残す」「行動を促す」という一連の流れを作れる強力なツールとなるでしょう。
そこにQRコードを組み合わせることで、チラシは「アナログ」から「デジタル」へと進化します。紙とデジタルのどちらか一方に偏るのではなく、両方の強みを活かすこと、それがこれからの地域ビジネスの販促に求められる戦略です。
「紙のあたたかみ」と「スマートフォンの利便性」、この2つを融合させることで、消費者の心に情報が届きやすくなり、確実に行動へ促す効果を発揮するでしょう
QRコードが、ポスティングを再び主役にする
ポスティングは一見、昔ながらの手法に見えます。しかし、「紙の強みを最大限に活かしつつ、デジタルへ自然につなぐ」ことで、現代の広告戦略の中でも十分に戦えるメディアへと進化しています。特に中小企業や地域密着型の店舗にとって、
紙チラシは「顔の見える広告」としての信頼構築に欠かせない存在です。そしてQRコードを添えることで、オンラインでの接点や顧客データ収集まで広げることができます。デジタルがあふれる時代だからこそ、人の手に届く「紙」の力を見直すこと。それが、地域の中で選ばれ続ける企業への第一歩となるでしょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、効果的なキャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
さらに紙媒体の強みを活かしつつ、デジタル広告と掛け合わせた次世代の販促方法についてもアドバイスさせていただきます。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
年末年始商戦に差をつける!あえてチラシの情報を減らす新常識とは
年末年始はさまざまな業種がチラシを配布するため、他社に埋もれない「本当に読んでもらえるチラシづくり」が必要です。本記事では派手さや情報量よりも「伝わりやすさ」を意識した、年末年始商戦を勝ち抜くポスティングチラシづくりのポイントを解説します。
情報は多すぎると伝わらない
ポスティングチラシをつくるうえで大切なことは、あれもこれもと情報を詰め込まず、「伝えたい情報」を絞るということです。
年末年始のチラシでは、多くの人が「できるだけ多くの情報を載せたい」と考えます。セール情報や商品の紹介、店舗情報やアクセス地図、クーポンなど、知ってほしい情報が盛りだくさんなためです。特に年末年始は一年の中でも売り上げも伸びやすい季節でもあるので、チラシに力が入るのは当然です。
しかし情報を詰め込めば詰め込むほど、読み手はどこを見てよいのか分からなくなり視線は迷子になってしまいます。
人がチラシを見て必要かどうかを判断する時間は、わずか3秒〜5秒だといわれています。その短い時間で「何を伝えたいのか」が明確でなければ、チラシは印象に残らずすぐに捨てられてしまうでしょう。
伝わるチラシでは、「何を言うか」より「何を削るか」が鍵となります。
情報を減らす勇気が成功を呼ぶ「ワンメッセージ戦略」
情報を盛り込み過ぎたチラシでは何が重要なのかが分かりにくくなると説明しましたが、チラシの反響を高めるためには、あえて情報量を減らす「ワンメッセージ戦略」がおすすめです。
「情報を減らす」というのは単に文章を削るのではなく、「主役を決める」という作業です。
すべてを並べて同様に扱うよりも、伝えたいメッセージを一つに絞り、それを軸に構成したチラシのほうが見る人に深く印象を残します。
飲食店であれば「忘年会予約受付中」よりも、「今年の宴会は“贅沢鍋”で温まろう」のように、一つの魅力を中心に据えてみましょう。
また美容院であれば、「新春キャンペーン実施中」よりも「2026年は、髪から輝く一年に。」のように感情に訴える一言を使うことで、印象に残りやすくなります。
減らした情報を補う「QRコード」
チラシの紙面では情報を減らし、スッキリ読みやすくすることをおすすめします。しかしもっと知ってほしい情報もたくさんあることでしょう。そういったときに、チラシにQRコードを載せることで、減らした情報を補うことができます。
QRコードからお店のHPやLINE、SNSアカウントに飛べるようにすることで、詳しいメニューやキャンペーン情報などを見てもらうことができます。さらにクーポンや特典などがあれば、より来店するきっかけとなるでしょう。
まずはチラシで関心を引き、詳細はWEB上で見てもらうよう誘導しましょう。
余白をつくることで読みやすくする
読みやすい・伝わりやすいチラシを作るうえで、「余白」を取り入れることは効果的です。チラシを作成するとき、空白があるとつい埋めたくなってしまうものです。
しかし実は余白こそが、デザインの中で重要な要素の一つとなります。
空白は「何もない」のではなく「伝えるためのデザイン」の一部であり、次のような効果を発揮します。
- 情報を整理して見やすくする
- 文字や写真を引き立てる
- 高級感や落ち着きを演出する
すべてのスペースに文字や写真を詰め込むと、読み手はどこを見ればいいのかが分からなくなってしまいます。逆に思い切って空間を残すことで、自然と目線がキャッチコピーや商品写真に集中しやすくなるでしょう。
特に年末年始のチラシは、色や文字が多いものが並ぶ時期。そんな中で余白を生かした静かなデザインは、逆に強い印象を与えます。「空間がある」というだけで、他のチラシよりも落ち着きや上品さを感じさせることができるのです。
訴求ポイントを一つに絞る
年末年始は、「お得情報」「期間限定」「新春初売り」など、訴求ポイントがいくつもあります。ですがチラシで効果を出すには、ポイントを一つに絞ることが何より重要です。
人の記憶は、一度に多くの情報を覚えられません。例えば「20%OFF」「抽選会実施」「福袋販売」などを同時に並べると、どれが最も重要なのかが判断しにくく、中途半端に見えてしまいます。
それよりも、「この冬、限定福袋だけで勝負!」といった形で一つの魅力を徹底的に目立たせる方が、記憶にも残りやすく訴求力が高いのです。
またポイントを絞ることで、デザイン全体にも統一感が出ます。
例えば「福袋」を中心に、写真やキャッチコピー、フォントやカラーなどを整えることで、パッと見ただけで分かる視覚的な説得力が生まれます。
チラシ作りの具体的なステップ
- まず「誰に伝えるのか」を明確にしましょう。主婦なのか、学生なのか、地元のファミリー層なのか、高齢者層なのか、ターゲットによって表現方法が異なってきます。
- 次に「一番伝えたいこと」を一言で言語化します。例えば「家族で楽しめる特別鍋」、「新年の髪型で印象アップ」など、印象に残りやすくします。
- そのメッセージを中心に、写真や色、レイアウトなどを整えます。
静かなトーンが、年末年始には逆に目立つ
年末年始といえば、そのおめでたさを表現するために、赤・金・黒・大きな文字・にぎやかな写真などを使った「勢い」と「華やかさ」があるチラシであふれます。しかし、消費者が一日に何十枚も派手なチラシを目にすると、視覚的に疲れてしまいます。
そんな中、「静かなデザイン」はかえって目を引く存在になります。白地を基調に、落ち着いたトーンでまとめたチラシは、まるで一呼吸置くように目を休ませ、自然と注目を集めるでしょう。
派手なチラシが多い中、あえて逆を行きギャップを作ることで差別化をはかることができます。
例えば、和食店の新春メニューなら、白と淡い金の組み合わせで「上品さ」を演出。住宅関連のキャンペーンなら、柔らかなグレーに明るいアクセントカラーを一箇所使う。美容サロンなら、背景を静かなベージュにして、商品の写真を大きく見せる、といった具合です。
こうした「静かなデザイン」は引き立つだけでなく、「このお店は落ち着いていて信頼できそう」という心理的効果も生みます。派手な広告が多い中で、トーンを抑えることが差別化の武器となるのです。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
年末年始商戦では、どうしても「目立たせたい」「売り込みたい」という気持ちが先行しがちです。しかし広告があふれる時期だからこそ、静かで整理されたデザインが伝わりやすくなります。
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。 チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ! 電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
2026年最新トレンド!年末年始・新年度に反響を得るチラシ制作のコツ
これから迎える年始・新年度は、一年のなかでも購買意欲が高まりやすく、チラシの効果を発揮しやすくなる時期です。同時に多くの企業がチラシを配るため、埋もれない工夫も必要です。2026年にチラシの反響率を高めるポイントを、5つの視点で解説します。
1.情報を詰め込み過ぎないシンプルデザイン
チラシ制作で起こりがちな失敗の一つに、「伝えたい情報をすべて載せようとする」ということがあります。チラシの読み手に伝えたい想いがあればあるほど、いろいろな情報を載せたくなってしまいますよね。
しかし2026年のデザインの潮流は、「シンプル」であることです。
人は情報が多すぎると、どれが要視すべき情報なのかが分からなくなり、結果的に何も印象に残らなくなります。だからこそチラシ作りでは、本当に伝えたいメッセージを一点に絞ることが大切です。
- セールなら「最大○%OFF」など、数字を大きく配置する
- 新メニューなら「この一品」にフォーカスして写真を大胆に使う
- 文字量を減らして「余白」を生かす
といった工夫が効果的です。
特に若年層やファミリー層では、普段からスマートフォンで情報を得る人が多いでしょう。SNSなどでも文章より写真・動画が好まれやすいこともあり、チラシにおいても写真を大きく使い、視覚的に訴えることが効果的です。
またスマートフォンのカメラでチラシを撮影して見る人も増えているため、小さな文字や細かい説明を避け、見出しと画像で直感的に伝えるレイアウトを意識しましょう。
「パッと見て理解できる」チラシが、最も反響を呼びます。
2.「オフライン×オンライン」の連動
2026年のチラシでは、紙だけで完結させない設計が必須です。 QRコードやSNSとの連携を前提にした「オフライン×オンライン」戦略が、反響率を大きく左右します。
QRコードでスムーズにデジタルへ
QRコードでデジタルへ誘導することで、紙面だけでは載せきれない情報を伝えることが可能になります。
チラシにQRコードを掲載し、キャンペーンページや予約フォーム、InstagramなどSNSに誘導しましょう。直接店舗のLINE公式アカウントへ飛ぶことができたり、Googleマップで店舗の場所を素早く確認できたりするなど、利便性を感じられる設計にすることが大切です。
2026年、さらにインパクトを狙うのであれば、QRコードの先に動画紹介やAR体験など、紙ではできないプラスの価値を用意することで、「チラシを持っていてよかった」と感じてもらえるでしょう。
チラシの配布に合わせてSNS広告を配信
最近ではチラシ配布のタイミングに合わせて、SNS広告を同地域に配信する手法も注目されています。
「ポストにチラシ」「スマホにも広告」という二重接触で、認知効果が大幅にアップします。
特に、年末年始や新生活シーズンは家族でスマホを見る時間が増えるため、SNSとの組み合わせは非常に有効です。
3.親近感が持たれやすいキャッチコピー
チラシの中で最も重要なのが「最初の一言」です。わずか数秒で読み手の興味をつかむためには、親近感と共感を意識したキャッチコピーが欠かせません。
2026年の傾向としては、「売り文句」よりも「生活者目線の共感メッセージ」が好まれる傾向にあります。
例えば
- 「今だけお得!」よりも、「がんばった自分に、ちょっとごほうびを。」
- 「新春セール開催中!」よりも、「新しい一年を、心地よくはじめよう。」
といった“やさしさ”のある言葉が響きやすい時代です。
また地域密着型ビジネスなら、「この街で20年」「○○駅前でおなじみ」など、身近さを感じさせる一言を入れるだけでも安心感が増します。
人は「自分ごと」として感じられる情報に反応するものなので、デザインだけでなく、言葉の温度にも心を配りましょう。
4.環境を配慮、サステナブルな素材
2026年は、チラシ制作にも環境を配慮した、サステナブルの波が本格的に広がります。
消費者の環境意識が高まる中、「エコな企業」「地域にやさしい店舗」という印象づくりがブランドの価値を高めます。
しかしチラシ作りにおいて、「環境に配慮する」ということにピンとこない方も多いのではないでしょうか。例えば、次のような取り組みがあります。
- 一度使われた紙などの古紙を再利用してつくられた、再生紙を使用する
- FSC認証紙(適切に管理される森林から生産した木材を使い認証された用紙)を使用する
- 植物由来インク(ベジタブルインク)で印刷する
- 過剰包装を避け、必要な枚数だけ配布する
これらの取り組みは、今後のチラシ作成においてもスタンダードになっていくかもしれません。またチラシの端に「環境に配慮した紙を使用しています」と一文添えるだけでも、企業イメージが大きく変わります。
消費者は、商品や価格だけでなく、その企業の姿勢や価値観にも共感して選ぶ時代となりつつあります。チラシという「企業の顔」から、環境に配慮した姿勢を発信することで、信頼と好感を伝えることができるでしょう。
5.2026年のトレンドカラーとフォント
チラシのデザインの印象を決める要素として、カラーとフォントの選び方も重要です。
もちろんチラシのテーマや企業のイメージなどによっても異なりますが、2026年には、「安心感」と「洗練さ」を両立したナチュラルトーンがおすすめです。
カラーのトレンド
- くすみグリーン:自然や調和をイメージし、リラックス効果を与える
- サンドベージュ:落ち着いた印象で、幅広い層に好感を持たれやすい
- ペールブルー:清潔感と未来感を表現しやすい
- モカブラウン:温もりを感じる色で、飲食・美容系にも人気
特に年末年始のチラシでは、「派手さ」よりも「上品な華やかさ」を意識すると差別化できます。赤や金を使う場合も、くすみトーンでまとめると一気に今っぽくなります。
フォントの使い分け
チラシのフォントでは、「読みやすさ」と「親しみやすさ」を感じさせることが昨今の主流となっています。
例えば次のようなポイントがあります。
-
遠くからでも読める読みやすさ(視認性の高さ)
→ 太さや間隔、コントラストがしっかりある書体を選ぶことで視認性が高まります。なかでもゴシック体はどんなチラシにも相性が良く、太字にすることでより読みやすくなります。 - チラシの情報の優先度を伝える
→見出しと本文でフォントを変えることにより、情報の優先度の違いを伝えやすくなります。大切なこと、最も伝えたいことは目立つフォントで分かりやすく伝えましょう。 - ターゲット層や業種に合っている
→女性を意識した美容系などの場合はやわらかい丸文字、高齢者向けのチラシでは上品さを感じさせる明朝体、男性的な建設業などのチラシは力強く、など、ターゲットの視点を意識すると、読み手に刺さりやすくなります。
また、文字色も黒ではなく「チャコールグレー」や「ダークブラウン」を使うと、優しく落ち着いた印象になります。チラシのイメージに合った文字色を選びましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
年末商戦はポスティングで差をつける!効果的なチラシ活用法
12月はボーナスやクリスマス、年末セールなどイベントが多く、購買意欲が非常に高まる季節です。特に年末は家庭でチラシを見る時間も増えるため、ポスティングの効果を発揮する絶好のチャンス!そんな年末商戦を勝ち抜くための、チラシ活用法を解説します。
年末に強い業種とその理由
年末の消費の傾向を踏まえると、需要が高まる業種がみえてきます。ここでは、ポスティングと相性がよく、年末に需要の高まる代表的な5つの業種を解説します。
飲食店
飲食店は年間を通して需要がありますが、特に12月は「食」を楽しむイベントがたくさんあります。例えば忘年会やクリスマスパーティー、家族の集まりなど、人と食事を囲む機会が増えるため、飲食店にとっては一年で最も忙しい時期となります。
そこでチラシにクーポンを付けることで「行ってみようかな」と思わせる動機づけに効果を発揮します。また「年内限定」「今だけ飲み放題割引」などの期間限定要素を強調すると、「期限が切れる前に行っておこう」と来店意欲を刺激できます。
小売店
小売店では冬物衣料をはじめ、クリスマスギフトや年末年始の福袋など、あらゆるジャンルの売り場で盛り上がります。
そんな小売店でチラシの効果を発揮するには、セール情報の「先出し」が鍵となります。
12月上旬から中旬にかけてチラシを配布し、他店よりも早く情報を届けることで、「もうそんな季節か」と消費者の注意を引きやすくなります。同時に「買うならここにしよう」と印象づけることができるため、「福袋予約開始」「年末セール先行開催」など、早めのアピールが勝負となるでしょう。
美容院・サロン
年末年始はイベントや人と会う機会が増えるため、「おしゃれをしたい」「きれいな自分で新年を迎えたい」という心理が働きやすくなります。そのため12月は、美容業界にとってもかき入れ時となります。年末直前は予約が取りにくくなるため、「早期予約割引」や「リピーター優先予約」などをアピールし、早い段階での来店予約を促しましょう。
地域限定のポスティングであれば、自宅近くで通いやすいサロンを探している人の目にも届きやすく、新規顧客の獲得チャンスとなります。
学習塾・スクール
冬休み前後は「冬期講習」や「新年度に向けた学習準備」など、学習関連のニーズが高まる季節です。特に年末は、保護者が子どもの進学や学習状況を見直す時期でもあります。
2学期の苦手なところを冬休みのうちにカバーし、3学期をスムーズに始められるようにしたい、と各家庭で意識するでしょう。そのため家庭のポストに直接届くチラシは、親世代への信頼感を与える有効な手段です。「冬期講習受付中」「新学年に備える〇〇コース開講」など、行動を促す具体的なメッセージを添えましょう。
不動産業
年末年始は、家族が集まり将来について話す機会が増える時期です。
「来春からの新生活」や「住み替え」、「実家のリフォーム」などの話題が出やすく、不動産への関心が高まります。普段は忙しく考える時間がない家庭でも、年末年始はゆっくり検討することができます。そのためこの時期に物件情報やリフォームプランをポスティングしておくと、年明けに動く層の意識に残りやすくなるでしょう。
年末の販促機会を逃さないために
年末は「イベント」「お金」「時間」の3つの条件が重なる、年間最大の販促チャンスです。そのためチャンスを逃さないポスティング計画が重要です。
具体的には、次のような機会を意識しましょう。
ボーナスシーズン
12月は多くの企業でボーナスが支給されるタイミングです。普段よりも財布の紐が緩みやすく、高額商品の購入やサービス契約が動きやすくなります。住宅や家電、車、リフォーム、旅行など、「少し贅沢な買い物」を提案するチラシは特に効果的です。
クリスマス
クリスマスはギフトを始め、外食やデリバリー、イベント関連など、消費が一気に高まる特別な行事でもあります。「家族で」「恋人と」「仲間と」など、ターゲット層ごとにメッセージを変えると、チラシの読み手への訴求力が上がります。またクリスマス直前ではなく、2〜3週間前に配布することで、計画的に動く層にも届きやすくなります。
年末年始セール
12月下旬〜1月初旬にかけては、小売店やサービス業ともに年末年始のセールで最大の繁忙期となります。「今年最後の特価」「初売り先取り」など、限定感と緊急性を打ち出すコピーが行動を促しやすくなり有効です。年明けまで見据えたPRをすることで、チラシの配布効果を長期間維持できます。
ポストが埋まる時期だからこそ「目立つ工夫」を
年末はどの企業も販促活動に力を入れるため、ポストの中は広告でいっぱいになります。そのためせっかくチラシを配布しても、埋もれてしまっては意味がありません。そこで重要なのが「他社と差をつける工夫」です。
デザインの工夫
年末年始のチラシには、赤・金・白・緑など、季節感のある色を積極的に活用しましょう。「年末感」「お祝い感」を演出することで、無意識に目を引く効果があります。また、写真やイラストを大きく配置し、パッと見て内容が伝わるレイアウトにすることが大切です。
キャッチコピーの工夫
長い説明よりも、短くインパクトのあるキャッチコピーが読み手に刺さりやすくなります。
例えば「今年最後のチャンス!」「年内限定〇〇割」「初回半額で新年を迎えよう」など、パッと見ただけで伝わる内容がよいでしょう。読者が「自分に関係がある」と感じられる言葉選びが大切です。
チラシのサイズ・形の工夫
チラシは一般的にA4サイズのものが多いですが、二つ折りや変形サイズを使うことも、チラシを目立たせるのに有効です。「なんのチラシだろう?」と手に取られやすくなり、開封率を高める効果があります。
クーポンや特典
「すぐ使えるクーポン」や「期限が近い特典」など、行動につながる仕掛けを入れるのも効果的です。「チラシ持参で10%OFF」「先着50名様限定」など、明確で使いやすい特典を提示しましょう。
配布タイミングを戦略的に
同じチラシでも、「いつ配るか」で反響率は大きく変わります。特に年末は、次のようなタイミングでポスティングすると効果的です。
給料日前後
月末は購買意欲が最も高まる時期です。給料日直後(25日前後)にチラシを配布すれば、「給料が入ったばかりだから買える」「頑張った自分へのご褒美に」という心理に刺さりやすくなります。
ボーナス支給時期
12月上旬〜中旬はボーナスの支給時期になります。大きな収入で財布の紐がゆるみやすく、普段は検討しにくい高額の商材や、大きな契約型サービス(住宅・車・リフォーム・保険など)を検討する人も増えます。このタイミングに合わせて配布すれば、反応率が一段と高まるでしょう。
週末前
家族で外食や買い物を計画しやすくなる、週末前(金曜〜土曜)に配布するのもおすすめです。「週末どうしようか?」という話題のきっかけとともに、情報収集の一つとしてチラシの情報が意識に入りやすくなります。特に週末にイベントがある場合は、チラシに大きくアピールしましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
年末は、「人の動き」「お金の動き」「気持ちの動き」が重なる絶好の販促時期です。このチャンスを逃さないためには、業種に合った訴求内容と戦略的な配布計画が欠かせません。
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
【初回ご依頼のお客様へお知らせ】
日本ポスティングセンターのHPへお越しいただきありがとうございます。
また、当社へのご依頼をご検討いただき誠にありがとうございます。
手前都合で大変恐縮ですが
現在、デザイン、ポスティングともにご依頼が混雑しており
年間を通しまして新規のご依頼枠が少なくなっております。
場合によってはチラシ制作、ポスティングともに
1か月~2ヶ月程度お待ち頂く場合がございます。
ご不便をおかけしまして誠に恐れ入りますが
ご依頼をご検討の際は実施希望日よりも
お早めに、日程に余裕をもってご相談頂けると幸いです。
何卒ご容赦下さいませ。
2025.10 日本ポスティングセンター
SNS広告×ポスティングで効果倍増!それぞれの特徴と使い方とは
長らくポスティングは有効な宣伝方法として活用されてきましたが、近年のSNSの発達とともにSNS広告を目にする機会が多くなりました。ポスティングのようなアナログ手法とSNSを活用したデジタル手法、双方の効果的な使い方を解説します。
宣伝方法の多様化とSNSの種類
インターネットの発達とともに、SNSをはじめとした宣伝方法の選択肢は増加しています。一方で、どれをどのように活用したらよいのか分からず、迷ってしまう方も多くいるのではないでしょうか。
宣伝広告に活用されるSNSにはさまざまな種類がありますが、代表的なのが Instagram 、X(旧Twitter)、TikTok、LINEでしょう。
Instagramは写真や動画を中心に商品の魅力を直感的に伝えることができ、若年層や女性向けの商材に強いという特徴があります。一方でX(旧Twitter) は拡散力が高く、幅広い年齢層のユーザーに対してのアプローチが可能です。特に短文での投稿や、キャンペーン情報を素早く広めるのに適しているでしょう。
Facebook は実名登録が基本のため信頼性が高く、中高年層やビジネス層へのアプローチに効果的です。そしてTikTok は、ショート動画を通じてユーザーの共感や話題性を生みやすく、若者を中心に拡散が期待できます。 LINE は日常的に使われるメッセージアプリですが、クーポン配布やリピーター獲得に効果的です。このようにSNSごとに特徴が異なるため、商品やターゲット層に合わせて使い分けることが成功の鍵となります。
そしてSNS広告が発達する一方で、ポスティングのようなアナログな宣伝手法も効果が見込めるとして現代でも重宝されています。このようにSNS広告の「デジタルメディア」とポスティングの「アナログメディア」を掛け合わせることで、より高い宣伝効果を見込めるでしょう。
SNS広告の特徴~メリット・デメリット
SNS広告にはポスティングとは異なるメリット・デメリットがあります。どのような特徴があり、どのように活用したらよいのでしょうか。
メリット
SNS広告には多くのメリットがあります。まず、年齢・地域・趣味関心など細かな条件で配信対象を絞り込めるため、ターゲティング精度が高く、効率的に見込み顧客へアプローチができます。さらにクリック率やコンバージョン数など、データを基にした効果測定が簡単にできるため、宣伝方法の改善や最適化がしやすい点も魅力です。
また少額から配信を始められる柔軟さもあり、中小企業や個人事業主でも導入しやすい広告手法といえます。
そしてなによりSNSでは、コメントやメッセージを通じて顧客と密に交流ができ、ファンづくりや長期的な関係構築が可能です。一度ファンになってくれた人はさらにSNSなどで情報を拡散してくれるので、二次拡散による口コミ効果も期待できるでしょう。加えてSNS広告では、ブランド認知や企業イメージの向上にも効果的です。動画や画像と文章を組み合わせて発信できるため、世界観や商品イメージをより強く訴求できる点も大きな特徴です。
デメリット
SNS広告にはメリットが多くある一方で、いくつかのデメリットも存在します。まず、スマートフォンやSNSの利用に慣れていない層には情報が届きにくいため、特に高齢者層へのアプローチは限定的です。またSNSは情報の流れが非常に速いため、せっかく配信した広告もすぐに埋もれてしまい、印象に残りにくいという課題があります。さらに広告感が前面に出すぎるとユーザーに敬遠されやすく、スルーされる可能性が高まります。そのため、自然な情報発信や共感を得られる工夫が求められます。
またSNSでの顧客との関係づくりには、効果が出るまでに時間を要します。一般的にSNSマーケティングでは、効果がでるまで1年程度かかるといわれています。そのためファンができるまでの間は宣伝の即効性が弱く、情報発信や交流の積み重ねが必要となります。
ポスティング広告の特徴~メリット・デメリット
ポスティング広告にはSNS広告とは異なるメリット・デメリットがあります。どのような特徴があるのでしょうか。
メリット
ポスティングには地域密着型のアプローチができる、という大きな強みがあります。チラシの配布エリアを細かく指定できるため、商圏内の住民や店舗の周辺に確実に情報を届けることが可能です。またチラシはポストに直接投函されるため、手に取って見てもらえる物理的な強さがあり、SNS広告のように情報が流れてしまう心配がありません。一度忘れられてしまっても、手元にチラシがあることで再度思い出してもらいやすくなります。さらにポスティングは、インターネットやスマートフォンの利用に慣れていない高齢者層やデジタルが苦手な人にも情報が届くため、幅広い年代にアプローチできる点も大きなメリットです。ポストに投函したチラシはすぐに見てもらえる可能性が高く、即効性が高い宣伝方法という側面もあります。そのため日が近づいているセールの情報やイベントの情報なども認知されやすいというメリットがあります。
デメリット
ポスティングにはデメリットも存在します。まず配布後に、どの程度の反響があったかを数値で把握することが難しく、効果測定が不十分になりやすい点が挙げられます。またチラシの印刷費や配布費用が必要となるため、配布部数が多いほどコストがかさむという課題があります。さらに受け取った人にとって興味がなければ、そのまま捨てられてしまうリスクもあり、必ずしも内容を読んでもらえるとは限りません。またポスティングの際にマナーが徹底されていないことで、クレームにつながる可能性もあります。クレームを回避するには、入念な下準備や工夫が必要になるでしょう。こうした点を踏まえ、チラシのデザインやターゲット地域の選定、ポスティングの方法に工夫が求められます。
「SNS広告×ポスティング」掛け合わせることで効果がアップ
ポスティングとSNS広告を組み合わせることで、それぞれのメリット・デメリットを補完し合い、相乗効果のある販促活動が可能になります。まず、ポスティングで地域住民に商品やサービスを「認知」させ、チラシにQRコードを入れてSNS広告へ誘導することで、興味を持った人に詳しい情報を「深掘り」してもらえます。またSNS広告でキャンペーンを告知し、ポスティングでは地域限定感を演出することで、購買意欲を高められる点も魅力です。さらに、オンラインとオフラインの両面から繰り返し接触することで、記憶に残りやすくなり効果的な宣伝につながります。地域特性やターゲット層に応じて、両者のバランスを最適化することが成功のポイントです。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、効果的なキャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
またポスティング作業では、研修を受けた自社の専属スタッフが配布しています。ポスティングのマナーを徹底し、過去の蓄積したデータや経験から、トラブルやクレームを未然に防ぐポスティングを心がけています。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
チラシは配って終わりじゃない!ポスティング後の反響率アップ戦略
ポスティングはチラシをポストに配るというアナログな宣伝方法ですが、最近ではSNSやWEBと連動して集客につなぐ動きが主流となってきています。反響率を上げるためには、むしろ配布後が勝負。ポスティング後にするべき反響率アップ戦略を解説します。
チラシからWEBやSNSへつなげる仕掛けづくり
チラシのような紙媒体では、記載できる情報量に限りがあります。そのためWEBサイト・SNSなどに誘導し、詳細な情報や最新のキャンペーンなどを見られるようにすることが効果的です。
チラシにQRコードを記載し、「詳しくはこちら」と文言を添えるなどして、簡単にWEBやSNSへ飛べる仕掛けづくりをしましょう。紙媒体とWEB媒体は別物ではなく、一つの流れとして設計することが大切です。特にSNSは双方向のコミュニケーションが可能となるので、顧客と継続的な接点をつくることができ、リピーターを増やしやすくなります。また商品やサービスを体験した人がさらにSNSなどで拡散することで、より多くの人に知ってもらうチャンスが広がります。
チラシだけでも十分に宣伝効果はありますが、まずはチラシのポスティングで「初回の接点づくり」とし、WEBやSNSなどと連携した戦略が最も効果的といえるでしょう。
SNSごとの特徴と関心の持たせ方
SNSにはInstagram、TikTok、X(Twitter)、LINEなどさまざまな種類がありますが、それぞれの特徴とともに違った効果的な見せ方があります。どのように活用すれば反響率を上げることができるのか、SNSそれぞれの特徴や関心の持たせ方を解説します。
Instagramは写真や動画が中心となるSNSです。そのため視覚的に伝わるよう、商品やサービスを見せる必要があります。特に第一印象が重要で、デザイン性やブランドの世界観を伝えるのに向いています。またInstagramではビジュアルが重視されるため、ファッションや飲食、旅行、美容などと相性がよいでしょう。飲食店やサロンでは 位置情報機能や口コミの利用で来店につながることも多くあります。お店の内装やサービス内容、メニュー、変化が分かるビフォーアフターなど、視覚的に伝わるよう発信するのに向いています。
TikTok/Reels
TikTokやReelsは、15秒〜60秒程度の短い尺の縦型動画が中心となるSNSです。そのため視覚的・聴覚的に分かりやすく表現する必要があります。特にTikTokはトレンド発信源としての役割が大きく、「リアル感・共感」のある投稿が好まれます。飲食店の場合は料理を作って完成する工程を短く編集したり、美容院などのサロンは施術シーンや、ビフォアアフターの変化を見せたりすると効果的です。
X(Twitter)
X(Twitter)は短いテキストが中心のSNSです。リアルタイムな情報を共有できる即時性が高く、ニュースやトレンドの拡散が得意です。利用者の年齢層も幅広く、特に20〜40代の利用率が高い傾向にあります。新商品の発売やイベント開催のお知らせ、キャンペーン告知など、リアルタイム性を活かした情報の発信が効果的でしょう。また「#キャンペーン名、#地域名」など、ハッシュタグをつけることで検索されやすくなります。
LINE
LINEは日常のコミュニケーションツールとして多くの人に使われており、メッセージが通知されることから開封率は圧倒的に高いとされています。公式アカウントを使えば友だち登録したユーザーに直接情報を届けることができ、リピーターを作るのに効果的です。飲食店や美容室、病院などの予約もできるので、クーポンの配布やキャンペーン告知に最適です。短くシンプルに、画像やスタンプを交えた親しみやすい文面 が好まれます。
ORコードを活用したチラシの反響率測定
チラシ配布後にどれほどの反響があったのかを測定することを効果測定といいますが、ポスティングにおいてチラシを配っただけでは反響を測定するのが難しい側面がありました。しかしチラシにQRコードを載せることで、LINEの友だち登録やSNSアカウントへ誘導できることから、ターゲットの行動データを細かく把握できるようになりました。
なかでもInstagramのインサイト機能では、投稿が表示された回数やクリック数などを把握することができ、自分のアカウントや投稿の成果を分析できます。どのような投稿が反響がよいのかも把握できるので、投稿時間や投稿内容を変えるなどして改善し、継続してユーザーの反応を測定することができます。
LINEの場合であれば、公式LINEの友だち登録数を見ることで反響をチェックすることができます。
チラシ×QRコードの効果的な使い方
QRコードを活用することで、どのように効果的な集客ができるのかをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
特典付きQRコード
「このQRコードから予約すると◯◯割引」「来店時にQRコード提示でプレゼント」といったように、QRコードに特典を付けることで、チラシを見た人の来店動機のきっかけを作りやすくなります。
動画・体験コンテンツにリンク
QRコードを読み取ることで、動画や体験コンテンツに飛べるようにします。動画ではチラシだけでは伝えきれない商品の使い方やお店の雰囲気などを見せることができるため、信頼感がアップし、来店意欲向上につながります。
LINE公式アカウントに誘導
「友だち追加でクーポン配布」「友だち追加でスタンププレゼント」など、LINE公式アカウントへ誘導することでリピーターの獲得や顧客との接点維持に効果を発揮します。一時的な集客だけでなく、継続的なつながりを作れるというメリットがあります。
キャンペーンやイベント専用ページへ誘導
チラシごとに異なるQRコードを作成し、どのチラシが反響を出したかを測定することができます。QRコードを読み取るだけでイベントの申し込みフォームや予約ページに直結させることで、ターゲットの即行動につなげることができます。
「アナログ」×「デジタル」の連携が大切
チラシの反響率を高めていくためには、WEB・SNS連携で得た反響率を測定・分析し次のポスティングに活かすことが大切です。分析したデータをもとに、配布エリアや時間帯、チラシの内容などを改善していきましょう。
ポスティングをしても、最初から反響を上げることは難しいかもしれません。しかし繰り返しポスティングをすることで、地域でも徐々に認知度は上がっていきます。
そうしてWEBやSNSと連携し繰り返しポスティングすることで、より反響率を高めていけるようになるでしょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ! 電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
あなたのチラシは大丈夫?チラシ制作で気を付けたい著作権
チラシ制作において、写真や画像を使用することはチラシを魅力的にするうえで欠かせません。しかしその選び方を間違えると、「著作権法」に触れてしまう可能性があります。チラシ制作をするときに気を付けたい、著作権の基礎知識を解説します。
著作権とはどんなもの?
著作権という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、それが何なのかを詳しく説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。
著作権とは「知的財産権」に含まれる法律上の権利のことであり、著作物を創った人の権利を守る目的で定められています。
例えば写真やイラスト、キャラクターやキャッチコピーなど、人が創ったものを他者が無断使用することは禁止されており、作品の権利は創作者に与えられます。
著作権はプロやアマチュアなど問わず、創作物を創った人すべてに、著作物が創られた時点で自動的に付与されます。
そのため意図せずとも他者の写真やイラストなどを無断で使用してしまうと「著作権侵害」として罰則が科せられたり、著作権トラブルに発展したりする可能性があります。そのため自分が創作していない写真や画像を使用する際には、十分注意しなくてはなりません。
チラシ制作をするときに注意すべき著作権
チラシ制作をするとき他社のデザインを参考にしたり、写真やイラストを載せたりすることは多々あるかと思います。しかし知らないうちに著作権侵害に当たる行為をしてしまっているケースも。チラシ制作で注意すべき、著作権のポイントをご紹介します。
著作権が該当する著作物
チラシ制作で写真やイラストを使用することはごく一般的ですし、目を引くチラシにするためにも重要な要素となります。しかし以下のものには著作権があるため、扱う際には注意が必要です。- 写真
- イラスト
- キャラクター
- キャッチコピー
- ロゴのデザイン
- チラシデザイン
- チラシ内の文章(商品の説明など)
インターネットの写真や画像には要注意!
インターネット上にはたくさんの写真やイラストなどの画像が掲載されています。その中から自社のチラシのイメージに合ったものを探すことは簡単かもしれません。しかしインターネット上に掲載されている作品すべてには著作権があるため、使用する際には注意が必要です。
インターネット上の画像を使用するためには、次のような選択肢があります。
- 「フリー素材」と書かれているものを使用する
- 有料の画像サイトで購入する
- 著作権利者に連絡し使用許可をとる
誰でも自由に利用できるとされている「フリー素材」であっても、商用に使用することはNGの場合もあります。商用目的で使用するときには、その画像が商用利用可であるかを確認しましょう。また画像の使用は可能であっても、画像を加工することはNGの場合もあります。それらの条件は著作権利者によって異なるので、事前によく確認しておきましょう。フリー素材であっても、撮影者名や取得元情報など使用元を掲載するとより安心です。
キャラクターの二次創作もNG
キャラクターを無断で使用することはNGですが、キャラクターを真似て自分で描く二次創作も、著作権法ではNGとされています。
キャラクターの一部だけの改変や、特徴が分かるものを使用するだけでも著作権侵害に当たる可能性があるので、チラシに使用するのは避けましょう。
また有名なキャラクターを使用する場合は著作権は創作者だけでなく、企業にも使用権がある場合があります。そのためキャラクターを使用する際には、それらの複数の著作権者に確認をとる必要があります。
チラシの文章にも要注意!
写真やキャラクターだけではなく、文章も著作権の対象物となるため注意を払いましょう。
一般的な会話に使われるフレーズや、「いらっしゃいませ」などのような商用によく使われるような表現は、著作権の対象から外れます。
しかし商品の説明文など、他者が書いたものをそのまま無断転載するのは著作権侵害に当たります。どうしても使用したい場合は引用しましょう。
著作権法を違反するとどうなる?罰則はある?
著作権を侵害すると、民事上と刑事上の罰則が与えられる可能性があります。どのような罰則があるのでしょうか。
民事上の罰則
著作権の権利者は、権利を侵害した者に対して次のような請求ができます。
- 侵害行為の差止請求(権利を侵害したチラシの配布中止・廃棄、デザイン等のデータの廃棄など)
- 損害賠償(権利者が被った損害に対する賠償金の支払いなど)
- 不当利益の返還請求(制作したチラシによって生じた利益の返還など)
- 名誉回復措置(訂正記事の制作、謝罪広告など)
これらの請求に対し侵害者側が適切な措置を行わない場合、民事裁判における使用差止請求や損害賠償請求などを行うことができます。
刑事上の罰則
刑事手続での罰則には、以下のようなものがあります。
- 「著作権法の権利侵害罪」著作権法119条1項より、10年以下の懲役、および1,000万円以下の罰金のいずれか、あるいは両方が科せられます。
- 侵害者が法人であった場合、著作権法124条より、3億円以下の罰金刑が科されます。
チラシでよくある著作権トラブル事例
チラシは身近な販促ツールですが、気づかないうちに著作権を侵害してしまうケースが少なくありません。実際にどのようなトラブルが起きやすいのか、トラブル事例を紹介します。
他社のチラシデザインをそのまま模倣する
チラシのデザインには創作物としての著作権があります。「デザインが素敵だから」と、他社のチラシをほぼそのまま模倣してしまうのは、著作権侵害に当たるのでやめましょう。
インターネット上の写真を無断で使用する
インターネット上の画像は基本的に誰かの著作物であり、無断利用は著作権侵害にあたります。そのため無断で使用するのはNGです。
アニメキャラクターを載せて配布する
子ども向けのイベントやキャンペーンで、人気アニメやゲームのキャラクターをチラシに載せる例があります。しかし、キャラクターには著作権や商標権があり、権利者の許可なしで使用することはできません。特に商用利用では大きなトラブルにつながりやすいのでやめておきましょう。
著作権トラブルを防ぐためのチェックリスト
著作権トラブルが起きてしまうと、「知らなかった」では済まされないケースもあります。あらかじめトラブルが発生しないように、次のことをチェックしておきましょう。
- 使用する素材の「利用規約」を事前によく確認しておく
- チラシに使用する画像などは、商用利用可のフリー素材を選ぶ
- 所有者が不明なものは使用しない
- オリジナルの写真やイラスト、文章などを積極的に使う
- 不安な場合は制作会社や専門家に確認する
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「著作権に不安がある」「より反響があるチラシを作りたい」「どんなチラシにしたらよいのか分からない」など迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206
ポスティングの反響率を上げたい方に以下の記事も読まれています!
マンションにチラシはNG?ポスティングできる集合住宅の見分け方
マンションのような集合住宅は、住居が密集しているため効率的にポスティングできます。一方でチラシ投函を禁止している物件も多く、その対応には注意が必要です。ポスティングがOKかどうかはどのように見分ければよいのか、また注意点なども解説します。
マンションへのポスティングのメリット
「チラシの投函禁止」とされているマンションが多くある一方で、わざわざマンションへポスティングするのにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ターゲット層が絞りやすい
マンションは戸建て住居に比べ、ターゲットを明確に絞ってアプローチしやすいというメリットがあります。
例えばワンルームマンションの場合などは単身者が多いため、宅配サービスや飲食、クリーニングなどのチラシが効果的です。またファミリー層向けのマンションでは、学習塾や子ども向け教室、不動産などと相性がよいでしょう。
このようにマンションは住民層が絞られやすいため、効率よくターゲットに情報を届けることができます。
効率的に投函できる
マンションは1 棟に数十〜数百戸あるため、短時間で大量に投函することが可能です。一軒家に1枚ずつ配るよりも、時間や手間がかからず効率的に宣伝することができます。
マンションにポスティングはNG?
近年、新築マンションや高級マンションなどでは、チラシの投函を禁止する物件が増加しています。その背景にはチラシによるゴミ問題や、チラシ配布を装った不審者がマンション内へ侵入することを防ぐ防犯上の理由などがあり、セキュリティを強化しているマンションへのポスティングはNGとなっています。
特にエントランスやポストに「チラシの投函禁止」「関係者以外立入禁止」と掲示してある場合には、クレーム
の原因になるため絶対にやめましょう。
とはいえ一律に「マンション=ポスティングがNG」というわけではなく、その建物ごとにルールが異なります。判断が付きにくい場合は、管理会社などに確認してみましょう。
ポスティングできる物件のポイント
「チラシの投函禁止」「チラシお断り」などの張り紙がない場合など、ポスティングをしてよいのか迷うところでしょう。次のようなケースではポスティングがOKな場合が多いので、参考にしてください。
「チラシの投函禁止」などの掲示がない
マンションの入り口やポスト周辺に、「チラシの投函禁止」などの掲示物がないかを確認しましょう。掲示されている場合はいかなる物件であっても、投函はNGです。
すでにチラシが投函されている
すでにポストにチラシが入っている場合は、ポスティングがOKだと判断する目安となります。
集合ポストが建物の外に設置されている
集合ポストが建物の外に設置されており、外部から投函できる位置にある場合はポスティングOKなケースが多いでしょう。
オートロックではない
マンションがオートロックでない場合、セキュリティもそこまで厳しくないため、チラシ投函への規制も厳しくないことが多いでしょう。
管理人が常駐していない
管理人がいない、もしくは不在時間があり常駐していない場合は、投函可能なことが多いでしょう。管理人がいる場合でも、許可を取れればポスティングできるケースもあります。
管理会社・オーナーの許可を得ている
管理会社やマンションのオーナーに事前に許可を得ることでポスティングOKとなるケースもあります。トラブルを避けるためにも、事前に確認するとよいでしょう。
ポストに鍵がついていない
チラシを禁止しているマンションでは、ポストに鍵を付け「チラシ禁止」の意思表示がなされています。そのためポストに鍵がついていない場合は、チラシ投函に対しそこまで厳しくないという判断ができます。
ゴミ箱が設置してある
エントランスやポストの周辺にゴミ箱が設置されている場合、ポスティングOKなことが多いでしょう。これはマンション側がチラシの投函があることを想定しているということでもあります。
築年数が長い
築年数が長いマンションは、新築マンションに比べてセキュリティ面が厳しくないケースが多く、ポスティングできるケースが多いでしょう。住民もチラシ投函に慣れているので、大きなクレームにつながりにくい傾向があります。
ポスティングするときはマナーを徹底しよう!
ポスティングはただでさえ、クレームが起きやすい宣伝方法と言われています。そのためポスティングするときには、マナーを徹底しましょう。
- 管理人に許可をとる
- ポストからはみ出さないよう投函する
- 床に散らからないよう気を付ける
- 住民に会ったら挨拶をする
- 清潔感のある服装をする
- 雨天時にはほかの郵便物を濡らさないように注意する
- 早朝や深夜のポスティングは不安を与えるので避ける ・
マンションへのポスティングでトラブルになるケースに注意
マンションへポスティングをする際に、どのようなトラブルが発生しやすいのでしょうか。注意点を解説します。
オートロック付きのマンションに入ると不法侵入になる
高級マンションや新築マンション、タワーマンションなど、オートロックの付いているマンションには勝手に入らないようにしましょう。 例えポスティング目的であったとしても、オートロック付きのマンションに許可なく入ると不法侵入にあたる可能性があります。警察に通報されることもありうるので、決して許可なく入らないようにしましょう。
何度もポスティングするとクレームの原因に
一度チラシを断られているにもかかわらず、何度もポスティングをするとクレームの原因になります。場合によっては住居侵入罪にあたる可能性も。一度注意を受けたら、必ずやめるようにしましょう。
エントランスが散らかりクレームの原因に
マンションの住民の多くは、チラシをあまり見ず捨ててしまいます。そのためエントランスのゴミ箱がいっぱいになり、散らかりやすくなります。またポストの奥までしっかり入っていないチラシが床に落ちる、ポストからチラシがはみ出していて見た目が悪い、盗難やのぞき見のきっかけになる、ということが懸念されます。投函するときはしっかりと奥まで入れるようにしましょう。
反響を獲得するなら、日本一高い「日本ポスティングセンター」へ!
日本ポスティングセンターでは、研修を受けた自社の専属スタッフが配布しています。ポスティングのマナーを徹底し、過去の蓄積したデータや経験から、トラブルやクレームを未然に防ぐポスティングを心がけています。
さらにスタッフにはGPS端末を持たせ、配布ルートの確認や不正を抑止する仕組みを採用。必要に応じて「GSP端末のデータ」も開示できるので、安心してご依頼いただけます。
また日本ポスティングセンターでは「反響率を上げるポスティングチラシのプロ」として、キャッチコピーやデザイン、ポスティング投函方法など、「捨てられないチラシ制作」にこだわったノウハウが豊富にあります。
「ポスティングを検討している」「どんなチラシなら反響率がアップするのだろうか」と迷われたら、一度日本ポスティングセンターにご相談ください。
チラシの反響率にこだわった豊富なノウハウで、読み手の心に刺さるチラシ作りのお手伝いをいたします。
またチラシ制作以外でも、ポスティングの単価や配布エリアのご提案まで、ご案内しています。
ポスティングのお見積りのご依頼、お問合せはお気軽にどうぞ!
電話でのお問い合わせは、こちら。0120-062-206